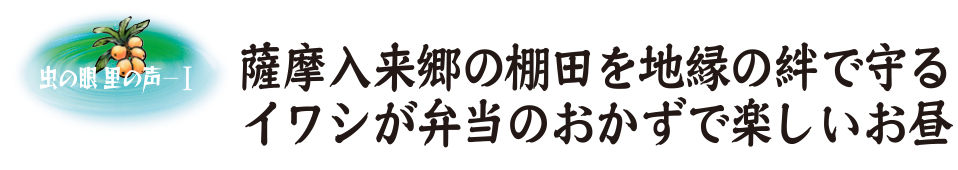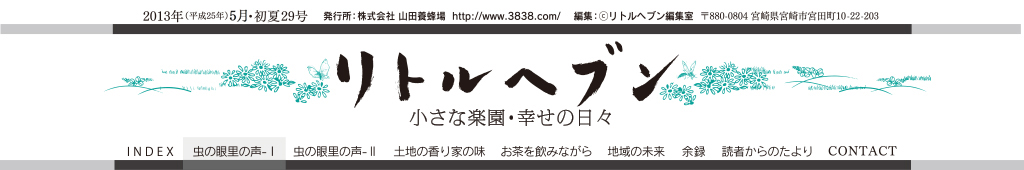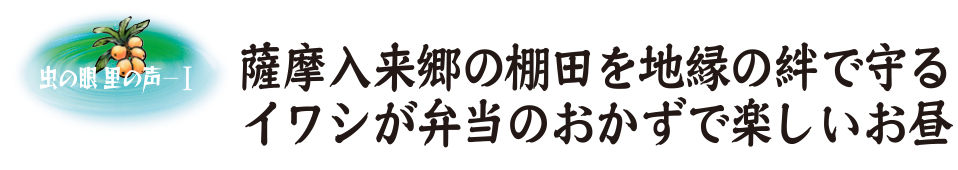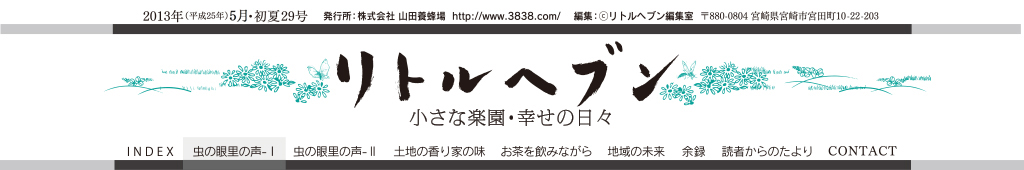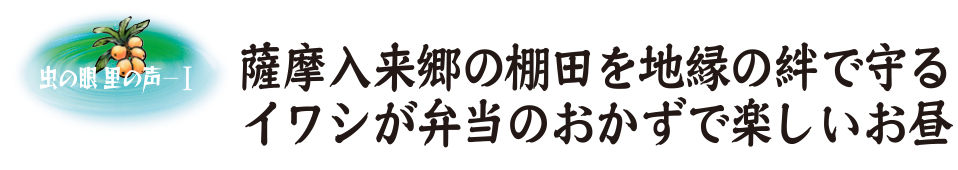原田茂治(はらだ しげはる)さん(62)は、3年前から毎週土日曜日には、農作業をするため鹿児島市内の自宅から棚田の一番上にある妻の実家に通ってきている。「今は空き家になっているので、棚田を荒らしちゃいかんと思って。楽しみはないですね、いつも独りですもん。独り寂しく仕事して、夕方早めに帰ります」と言いながらも、今日は、大勢の人が手伝いに来てくれて仕事に張り合いがあるようだ。
参加者が張り付くように作業を始めたのは、棚田にしては広い一反歩ほどの田んぼの土手だ。以前、道博さんが牛の飼料用にトウモロコシを植えたら、鹿が来て「全部やられた」と恨みのこもる田んぼだ。鎌で土手の草を払い、ヤンカ(山鍬)で土を剥がしていくと、中から立派な石垣が姿を現した。内之尾集落の先祖が、汗と涙で築いたといわれる石垣だ。「集落には家系図がないから、私の5代前まではさかのぼれるけど、それ以前のことはね。この石垣がいつできたか分かりません」と、道博さんは残念そう。
誰もが黙々と、自分の目の前の石垣に取り組んでいる。「ああっ、マメが出来た、こりゃ」と、正裕さんが右掌(てのひら)を見つめている。腰が痛いと嘆いていた力さんが「日当次第では、腰もバンと伸びっとやが。1日2万円もくれりゃな」と、おどけてみせる。その後で「ここで生活して楽しいと思ったことはなか、こんな山ん中」と力さんは、ちょっと真顔になった。
遠くの有線放送から「野バラ」のメロディが流れてきた。12時のお知らせだ。
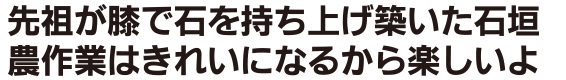
鹿児島県薩摩川内市入来町内之尾集落には、現在17世帯が暮らす。集落は、清浦川の支流になる内之尾川上流域北側の集落と下流域の南側に点在する集落の2つに分かれている。鹿児島市との境をなす八重山(やえやま・677m)の中腹に位置し、石垣の美しい内之尾の棚田は1999年の農林水産省「日本棚田百選」に選ばれている。
「入来町誌」によると、明治初年の入来郷の人口は4515人となっている。町誌は、それ以前の100年間で約1000人の人口増加があったため、この頃に入来郷周辺の新田の開発がなされたのではないかと推察している。内之尾集落の位置を考えると、ここの棚田も同じ頃に築かれたと推察できる。
「この石垣は、先祖が膝で石を持ち上げて築いていったんだよと、うちの夫(ひと)の親が言ってましたよ。昔の人は、体で作ったんだから」
こう言うのは、脚立を立てかけて高い石垣の草取りをしていた有馬(ありま)マツヱさん(75)だ。棚田保全グループとは別に、夫の秀夫(ひでお)さん(85)と2人で、5枚の棚田3反3畝の米を作っている。25年前に内之尾集落から町の中心部に近い副田(そえだ)地区に引っ越したが、「ここだけは作らないかんと思って」通っているのだ。
「農作業が楽しいよと若い衆に言えば、何が楽しいと言うけど、農作業はきれいになるから楽しいよ、と言うんですよ。町の人は違いますよね。生きがいで田んぼに来ていますよ。もういっときしたら、この石垣の中にマムシが入るんですよ。だから今のうちにきれいにしとかんと、マムシは土色をしとるから見えんですがね」
話を聞いているうちに、夕方5時を告げる「野バラ」が流れてきた。棚田の上の段で枯れ草を燃やしていた秀夫さんが、「もう5時、帰ろう」と催促に来た。
「田んぼに水を入れるのは、6月になってから。何回も水をやって代掻きをせんと、水の溜まりが悪いから。高い石垣のところは、だいたい水持ちが悪い訳ですよ。それでも代掻きを何回もすれば、水持ちが良くなる訳ですよ」
何気ない言葉だが、棚田で米作りをするのは、平地の田んぼにはない苦労があることが伝わってくる。