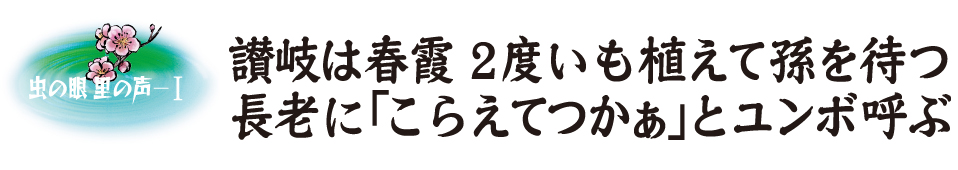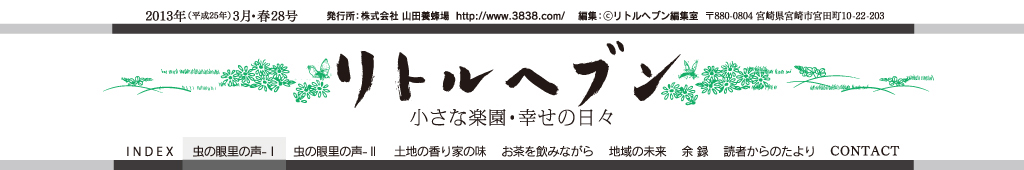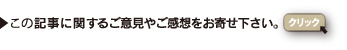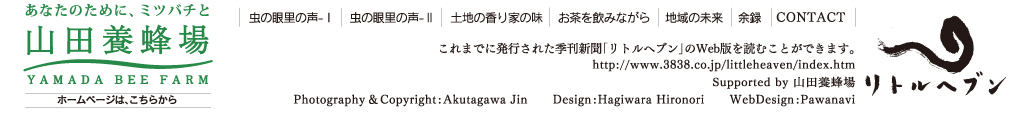「この前やったんから、もう20年になるじゃろ。もうなんぼ長生きしても、次やるまでに命がないわ。最後のご奉公や」と、ため池に溜まった砂を鍬で掬いながら、多田武士(たけお)さん(73)が冗談めかして言う。武士さんと長尾槇次(まきじ)さん(78)が、作業に参加している中では長老格だ。ユンボが通って泥で汚した道路の掃除を、日出夫さんが、参加者を気遣って簡単に切り上げようとすると、「道路汚したままで終わったら、あかんぞ」と、槇次さんの叱責が飛ぶ。その一声に反発する者はなく、再び、道路に撒き散らされた泥を取り除く作業が始まった。役職は役職、長老には長老の重みがあるのだ。
作業は昼前に終わった。日出夫さんは、水利組合長の役目柄最後まで残らなければならない。皆が三々五々帰宅するのを見送りながら、ため池の堤に立って水田の広がる本村下の風景を見下ろして誰に言うともなく呟いた。「改めて見ると、ええ景色やな。全部うちの庭や、そやからうちでは、庭しよらん」。

穏やかな春霞の日が続いていた。冬耕の終わった田んぼは、春の日差しを浴びて心なしか盛り上がって見える。畦道を歩いていると、所々で、ふいに梅の香りに気付く。ほとんど車の通らない「ふれあい農道」と呼ばれる広い2車線道路が、真っ直ぐに伸びている。その脇の畑で、男性が水やりをしていた。「タマネギは、今からがいに(沢山の)水が要るんじゃ」と、上城栄さん(84)がホースを引っ張りながら畑を行ったり来たりしている。
香川県木田郡三木町本村は、3地区に分かれている。下(しも)が14戸、中(なか)が8戸、上(かみ)が10戸の集落だ。南北に長い三木町のほぼ中央の西の端に当たる集落で、高松市と境を接している。「ここは昔から開けとって、学校もあったし郵便局もあった。うちの家んとこが学校やったんです。学校いうたって、旦那がしよったんやろけど」と、下の自治会長を務める川田敏美さんが、ちょっとだけ自慢げに教えてくれた。栄さんの家の前に土塀で囲まれた大きな家がある。集落に2軒か3軒、旧家があって、その旧家が、集落の土地と山を所有していた時代は、地域の人々は旧家を「旦那」と呼んでいた。「旦那さんに年貢を持って行きよったんじゃ、米をの。我々は、田んぼの小作じゃけん。戦後の農地解放で、わしらも土地持ちになれたんじゃ」と、栄さん。
水やりをしながら、傍に着いて離れない私に、栄さんが語りかけてくる。
「ここら辺の衆は、跡取る者(もん)一人だけ家に置いて、後の者は口減らしいうてな、学校が済んだら皆出て行きよった、15歳くらいから。うちでも妹が2人おったけど、大阪へ行ったんじゃ。女中や子守じゃいうてな。女中しもって勉強しよったんじゃろ、看護婦さんになって、妹を呼んでくれてな、嬉しかった。それぞれ学校済んだら、居らんようになるんじゃ。そないな世の中じゃった、前はな。つまらん世の中やったけん、生き抜かないかんけん。一生懸命働いて、40年ぐらい前にハウスで、三木町で初めてイチゴ作ったんじゃけど、去年ハウス壊してしもた。腰を屈(かが)めての仕事やから、どうしても体をやられる。脳梗塞になってな。ハウスの中にはまって、下向いて仕事しよるけんの。うまいこと治って良かった。長いこと入院しとった時に、この三角の山が、城山(じょうやま)いうんじゃけど、医大の6階からよう見えるんで。懐かしい、うちがあの下じゃがと思うて」
栄さんが水やりを終えたタマネギの畝で、妻のキミ子さん(83)が腰をくの字に曲げて草取りを始めた。その姿を見て栄さんが愛おしそうに、私に言う。「20年も、腸が、いがんどった(曲がっていた)のを辛抱しとった」。キミ子さんは、タマネギの畝の小さな草を、鎌の先で掘っては一つひとつ抜いていく。遅々として進まないように見えるが、いつの間にか、タマネギ畑は草一つないきれいな畝になっていた。

田植えまでに残す2ヶ月の間、せっかくの春の日差しを活かすため、ジャガイモの植え付けが始まっていた。しっかりと角の尖(とが)った立派な畝に「秋ばれ」と「男爵」の種芋を一つひとつ並べて置き、その上に薄く土を被せて肥料を蒔いて、さらに霜除けに籾殻を被せていく。長尾槇次さんの仕事は丁寧だ。
「一年一年、体がくたびれてきよる。ひとりで7反ぐらいの田んぼをしよるんじゃけど。臑(すね)が悪うして杖が要るんじゃ。野たれ作じゃ、やりかねよる言う意味よ。親父が長いこと村会議員しよった時には、無報酬やったんや。とにかく他人(ひと)のことやったら、うちの仕事放っといてでもしよったで。それで、わしは中学1年の時から牛を使いよったで。今はもう子どもらは皆、独立してひとりでやりよる。30年くらいタバコ作って生計立てよったけど、今が一番ええんじゃないかと思う。気は楽になりました。歳をとったら、酒でも飲まな何の楽しみがあるかと思うけどな」
ひと休みしている間、槇次さんの身の上話を聞かせてもらった。「腰は痛い、臑は痛いし、もう」と、少々愚痴りながら天鍬(てんぐわ)を持って畝の仕上げに掛かった。鍬の左右で交互に土を掬い上げて畝に土盛りし、真っ直ぐ手前に引いて大量の土を掬い上げる。ひっくり返して鍬の背で土をかき集め、平たく打って土の塊を崩す。一本の天鍬が、千変万化の活躍だ。槇次さんの熟練された農術を、目の当たりにする思いだった。