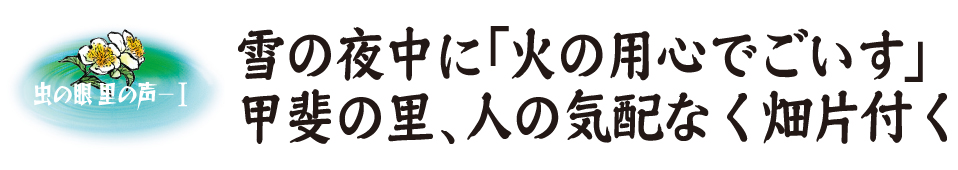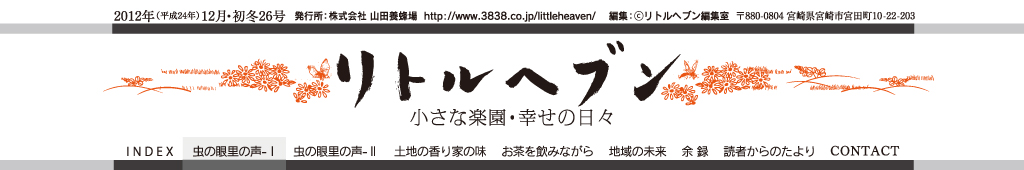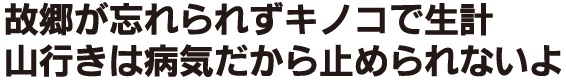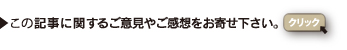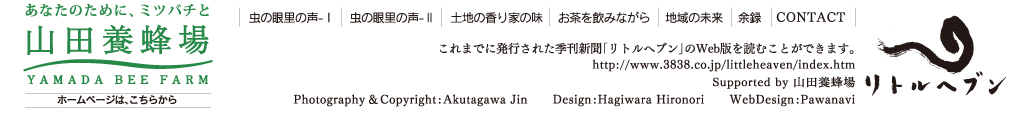「火の番板が、自分の家に来ていた時に雪が降るとね、向こう3軒でね、時間を決めて吊り橋の雪掻きに行くですよ。うんと降る時にはね、帰る時に、また掻きたくなるくらい積もるですよ。とにかく長さ160m、幅2mの橋ですから。帰ってくると『火の番板だよ』と板を次へ渡してきちゃう。この降りじゃ、すぐ行った方がいいよ、ということになるし、夜中でも、ぐずぐずしているとね、雪が積もってね、その重みでね、橋を落としてしまうと交通手段はありませんから。160mを3人で掻くのだから、次の人たちもすぐ行くですよ。その次の人もすぐ行くとね、ひと晩のうちに、又、回ってくる時もあるですよ。寝ている暇はないですよ、ええ」
ちょうど火の番板が回ってきている実江さんも、吊り橋当時の雪掻きの大変さを思い出したようだ。「夜中だからね。60cmも70cmも、みゃくみゃく降るだからね。1時間おきに板が回ってきて、夜中の1時でも2時でも、雪掻きに行ったですよ」。
その吊り橋を支える県道側の金具が、雪の重みで壊れ、橋が傾いたことが一度だけある。1946年(昭和21)のことだ。
「ワイヤーの一本がちぎれて傾いてね。落っこちやしなかったけど。復旧もかなり時間が掛かりましたよ。そん時には、当番の人たちは、かなり責任を感じたでしょうね。誰であったか、よく分からないけどね」。当時、中学生だった俊英さんは、山越えの道を通学したそうだ。大人たちは、冬で、水が少なくなっている早川の河原まで降りて、水が流れている所には丸太の橋を架けて対岸まで渡った。
家の人は寝ていても、雪の夜に「火の用心でごいす」と声を掛けて回った早川集落100年の汗と涙の歴史が、二つに割れ、角が丸まった火の番板に染み込んでいる。
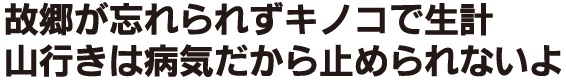
南アルプスの紅葉が見頃となった週末、南アルプス公園線の愛称を持つ県道37号線には、首都圏や東海地域のナンバーを付けた自家用車が押し寄せた。早栄橋たもとの県道沿いに「早川きのこ園」の看板を立て、庇(ひさし)の下にパック入りの様々なキノコを並べた店が出ている。早川町は多雨冷涼地域であるためキノコが育つには好条件なのだ。店の主である早川正治(しょうじ)さん(58)は、高校を卒業した後、東京や甲府で会社勤めをしていても、故郷の自然の中で暮らしたいと思い続けていた。父親の体調が思わしくなかったため、帰郷して実家の養豚を継いだが、1987年(昭和62)からはシイタケ栽培に切り替えた。店頭に並んでいるのは、ナメコやクリタケ、ムキタケ、ヒラタケ、ナラタケ、生シイタケなどと、マツタケが2本入った1万2千円のパックも並ぶ。
「本数は少ないですけど、マツタケも採れますよ。早川は、温度差が大きいのが良いけど、雨はもっとあった方が良いね。キノコで生計を立てられると思って始めたけど、今は、外国産に押されて価格破壊でね。それでも、山へキノコ採りに行くのは病気だから、雨が降ろうが体調が悪かろうが、止められないよ。キノコ採りは、保育園の宝探しみたいなもんですよ」
翌朝、クリタケを採りに行く正治さんと一緒に山へ入った。山へ入ると言っても、早川集落がそもそも山の中にある。集落から車でわずか2、3分。杉林の中の比較的平坦な場所を利用し、自然の中でクリタケ栽培をしていた。最低限の環境整備をしてキノコの菌を植え付けるだけ、後は、自然の条件に任せてキノコを栽培しているのだ。ひんやりした空気が漂う杉林の中に入っていくと、番犬の「悟空」が尻尾を振って飛びついてきた。「山の中で独りにしておくのは可哀相だけど、鹿や猿がキノコを食べに来るのでね」。正治さんは、悟空の頭をちょっと撫でてやると、斜面になっている林の奧へ小走りで入って行く。後に続くが、正治さんの姿はすぐに見えなくなった。音を頼りに追い付くと、すでに幾つかのパックがクリタケで一杯になっている。「このクリタケは極上ですよ。私が食いたいくらい」と、嬉しそうにパックのキノコを見せてくれた。
朝、採った新鮮なキノコを店頭に並べるために、時間と勝負のキノコ採りだ。 小走りで次々と場所を移動し、クリタケとナメタケでパックが一杯になると、すぐに店開きである。